診療の中で
産業医の発言
2021年02月10日
産業医の職務は、健康診断結果に基づく措置、長時間労働した場合の面接指導、作業環境の維持管理、衛生教育などを行い、働く人の健康管理を担うことにある。これらに加えて、より適切な管理を行うため、職場巡視をして、さらに、衛生委員会に参加する。私は、いくつかの職場でこの役割を担っている。最近になって、ある職場で、あるエピソードがあった。
衛生委員会は、事業所から生じる安全や衛生問題などを討論する場であり、私が出席する際には、その都度、産業医としての意見を述べている。そのほとんどを、会議の終わりに総括する形で締めくくる。ある職場で会議を行ったときのことである。いつものことながら、事前に最近問題となっている事柄をまとめて会議に臨み、さらに、会議の途中で気になったことを書きとめて、最後に発言する用意をしていた。しかし、進行役は、私にコメントを求めることなく会議を終わらせた。追加発言すればよかったのであるが、喫緊の問題でもないし、何だか差し出がましさを感じたから何も言わなかった。次も、その次も同じような具合で会議が終わった。
私は、この調子だと産業医が会議に出席する必要がないと思ったので、終わりのあいさつ(実に、始まりと終わりに起立してあいさつを唱和するのである)をする前に、進行役にひと言を発した。私に会議についての意見を求めないのなら、今後この会議に出席しなくてもよいのでは、と皆の前で言ったのである。その後、責任者と三者で話し合い、毎度発言の機会を設ける旨を申し合わせた。
次に訪問した時、会議の事項書をみると、責任者のあいさつの次に産業医あいさつと書かれていた。書かれているのだから、はっきりとして良いと思ったものの、私と責任者のあいさつを並べるのは仰々しいと思ったのである。また、会議を産業医として総括することのほかに、冒頭にあいさつすることを設けてもらうと、発言する機会が多くなり過ぎて、活発な意見交換が出来るだろうか。そんなことを打ち合わせた結果、他の職場と同じように、会議の終わりにコメントを求められて意見を述べるということとなった。
こんなちっぽけなことを取り上げたのは、何か事が運ぶ際に、そのこと自体が形を整えるだけで、中身を掘り下げることなく有名無実化しているのではないかと危惧したからである。会議でいえば、進行して形だけ終われば良くて、本来の趣旨を疎かにしている。まさに形骸化していると思うのである。私は、冒頭に記した産業医の職務を実行するために、ある緊張感を抱きながら発言している。すなわち、その都度真剣勝負にも似て臨んでいるのである。ところが、件の職場で体験した進行具合は、私に付け入る「隙」を見せなかった。
このような会議のエピソードを教訓にすると、周りに同じようなことが多く見つかると思った。職場を活性化させることは悪いことではない。しかし、本来あるべき活性化を形骸化が阻んでいると改めて思う。周りだけではなく、私が担っている職場も、私の医院も、何か滞ったことがないかと、見直してみようという気になった。どんな組織も制度化されてしばらく経つと、旧くなるものである。陳腐化するに任せるのではなく、魂を入れれば、それに見合う効用があると思った。
肘内障
2020年10月12日
小児には、入院治療を必要とする病気から、医院で治療できる病気まで様々にあることは言うまでもない。その中で、川崎病は、発熱、頸部のリンパ節腫脹、眼の充血などを主症状とする症候群で、のちに心臓血管に冠動脈瘤を生じさせることがあるため、出来るだけ早いうちから治療を行わなければならない。私のような開業医の立場では、疑いを持てば症状が出揃う前から病院に紹介することが肝要である。
また、肘の靭帯から骨がはずれかかる肘内障にしばしば遭遇する。主に、手を引っ張られたことにより発症し、子どもは痛がって腕を動かさなくなる。しかし、治療、すなわち整復をすると、泣きわめいていたのが急に穏やかになり、その場で遊び始め、治ったことがはっきりとわかるのである。肘内障は、川崎病とは違って、開業医が診断し治療することが出来て、しかも、すぐさま治る病気である。
この2つの病気を診断することに共通しているのは、開業医としての役目を果たしたという充実感が殊の外強いということである。前者の川崎病は、診断が手遅れになると不利益が測り知れなくなる。そのため、診断に臨む際の「緊張」が、病院から返事をもらった後の「弛緩」へ変わるという殊更得がたい経験を持つことになるのである。後者の肘内障では、症状が急激に消失し、もとの元気な姿を目の当たりにする。その痛みも何もなく普通に遊んでいることが愛おしく感じ、まるで、珠玉のひと時が診察室に用意されるが如くである。
さて、その肘内障を近ごろ治療してから、ある想念が浮かんだ。それは、古希を迎えた開業医には、どのような仕事が相応しいかということを際立たせようと思ったのである。思えば私は、仕事を徐々に縮小させてきた。すなわち、病院に治療を委ねることが早くなり、しかも多くなったように思う。開業当初は、心不全を起こした患者さんを往診しながら治療した。それは、開業する直前まで勤務していた病院で行っていたことを、場所を違えて行ったに過ぎなかった。しかし、私が昼も夜も仕事をする体力がなくなったことなどを理由として、早めに病院に紹介するようになったのである。それは、適材適所ということなのだろうと思う。おそらく、これは年を取るにしたがって重みを増す言葉にちがいない。
肘内障を患った子どもの元気になった姿に象徴される診療の在り方が今の私に相応しいとつくづく思う。診療に気を抜ける疾患などない。しかし、一人が何もかも診療できるわけではないことは自明のことである。確実に年を重ねるなかで、改めて領分をわきまえたいと思う次第である。
希望するもの、抗体検査と発熱外来
2020年04月24日
新型コロナウイルスによる感染について、日々情報が多く出されている。
4/24にインターネットで知ったことである。ニューヨーク市の住民を無作為で選んだ人を対象に新型コロナウイルスに対する抗体検査を行った結果、21.2%の人が抗体を持っていたらしい。これが事実だとすると、新型コロナによる感染致死率が0.5%に低下するとのこと。これは、予想を超えて感染した人が多く、しかも治っていたということであり、おそらく、症状のない不顕性感染も含まれていると思われる。
この新型コロナウイルスに対する抗体が、麻疹に罹って獲得するような終生免疫となるのか、あるいは、インフルエンザのように一定期間免疫を有することになるのかが、気になるところであり、今後迅速に研究されることを願っている。
日本でも、この抗体検査を国民すべてが行えるような施策を望む。それと同時に、各地に、発熱専門外来を作ってもらい、誰もが遠慮なく診察できるような体制を願う。ここは、発熱者が隔離されて個別で診察を受けることができて、新型コロナのPCR検査も受けられて、感染が判明すれば、すぐに治療を始める準備ができることが望ましい。今は、感染を恐れて受診を控える患者さんが多いし、もし医療機関で新型コロナの感染者が判明したら、感染濃厚接触者とされて、診療が当分の間できなくなるという状況では十分な診療ができない。
正しく恐れる
2020年04月24日
テレビで、バッハ作曲、無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番を聴いていたときのことである。途中で、ついさっきまで見ていた、新型コロナウイルス感染症のニュースが浮かんできて、そういえば、医師会から医療機関がどのように対応するかの指針が毎日のように届いていることを思い出した。
以上のように記したのは2月のこと。それからの2か月、新型コロナウイルス感染の急な拡大は周知の事実である。多くの専門家が記しているように、数日も経たないうちに、書いたことが古くなってしまうほど病気の蔓延が早い。感染者数は、急激な上昇カーブをえがいて増加している。皆が病気の感染を身近に感じて、恐怖を抱く状態が続いている。そんな中、4月中旬の三重県知事の会見で、患者の家に石が投げ込まれたり、壁に落書きされたりする被害があると発表していた。危機に際して、人間の嫌な面が出た典型的なことである。私は、この危機を抱く感情を和らげるのは、医療者の務めであることは当然のこととして、何とかならないだろうかと考えていた。これは感染症に対して忌み嫌うという感情そのもので、それは、過去にハンセン病に対する差別、今もあるインフルエンザに抱く感情につながるものである。ウイルス、細菌という微生物が相手であり、なかなか正しい知識を得ることができないことも拍車をかけていると思うのである。私は、そんなことを踏まえて、新型コロナウイルス感染症とも関連する肺炎を、その死亡率について改めて調べてみた。そして、新型コロナと比較するために、インフルエンザの動向も併せて、厚生労働省の人口動態統計をみてみた。
肺炎の死亡率は、3位から5位と高い。2018年には94,654人が、その2年前の2016年には119,300人が死亡している。年齢階級別では、60代が人口10万対で21.0、それより高年齢ではさらに高くなり、数字の上では低い若年齢層も含めて、すべての年代にわたって死亡者がいる。また、2018年にインフルエンザで死亡した人は、3325人に上っていて、さらに2019年1月には1か月で1685人が死亡し、一日平均54人が亡くなった計算である。
さて、新型コロナウイルスによる死亡数は、目下300人に達して、感染者数も12,000人を超えた。この死亡数を感染者数で割ると、2.4%となる。一方、例年インフルエンザに罹る人は、1000万人を超えていて、死亡した3325人を感染者数で割ると、0.03%である。また、直接的及び間接的にインフルエンザの流行によって生じた死亡を推計する超過死亡という概念があり、日本では死亡数が1万人と推計されている。超過死亡で計算しても0.1%であり、死亡した割合は、新型コロナのほうが多く、このことが治療薬もないことと相まって、今の恐れにつながっているのではないだろうかと推測する。ただ、インフルエンザで死亡する人が毎日54人いたという事実は、メディアによる報道がないことから、恐れられていない。いや、話題に上っていない。これら、片手落ちのようなこともあって、いまは正しく恐れるのではなく、いわば偏った恐れになっていると思うのである。
件の三重県知事の会見で明らかになった、心ない振る舞いをした人は、肺炎の死亡数やインフルエンザの死亡数を知っているだろうか。もし、この大きな数字を知ったときに、同じ振る舞いをするだろうか。私は、メディアを始めとしたアナウンスの難しさを思う。限られた時間の中で、何もかもを報道できるわけではない。しかし、平時にはおそらくおとなしくて、攻撃性もなさそうな人が、危機に際して憎しみをぶつけてくるというのも、今のメディア環境と関連がないわけではないと思うのである。
2月に聴いたパルティータは、終曲にシャコンヌが用意されている。その巨大さは群を抜いている。もともと低音が鳴らないヴァイオリンであるのに、オーケストラを思わせるように音が拡がり、重なる。長い曲を奏でる演奏家の一所懸命さが伝わる一方で、バッハ自身は泰然自若としているが如くの内容なのである。曲の終わりには冒頭のメロディが再現され、宇宙の下で衆生は輪廻しているということが思い浮かぶ終曲でもある。
バッハの曲は、地球だけではなく宇宙全体を鳥瞰するような気分にさせられる。今の危機を宇宙の中に相対し、診察室で診療にあたりたいと思う。ひいては、憎しみを和らげられることを念じながら。
風邪と診断する
2019年08月25日
この夏も、小児を中心に手足口病が流行した。ある患者さんの保護者が、インターネットで調べたところ、手足口病ではないかと思い、診察に来たと言っていた。子どもの手足には、典型的な発疹があり、私は追認して、これからの過ごし方を話したところ、ネットに書いていましたと、すでに対処方法も知っていたようだった。もしかしたら、私の知識より多いと思えるような保護者の話しぶりであった。私はかねがね、患者さんに知識が増えることは、病気を介在とした医者、患者の在り方を考えるきっかけになることがあり、どちらかというと好ましいことであると思っていた。そして、私の開業年数を重ねるにつれて、徐々にそのようになってきている。
話しが変わり、いささか旧聞に属するが、福島第一原発が震災にあった直後から、事故に対応するため、東京電力本店と現場とでテレビ会議を行っていた。その会議の記録をAI(人工知能)で分析したところ、現場で指揮をした故吉田所長が徐々に極限の疲労状態に達していたことが判明したという。AIによって、日本語の自然言語処理を施したらしいが、仔細は『福島第一原発1号機冷却「失敗の本質」』に書かれている。どうも、AIは感情や心の動きがわかる段階になっているようなのである。また、医療の分野でも、MRIなどの画像や細胞の診断に活用されつつあると聞く。すでにAIが医者に取って代わり、医者の存在感を少なくしている。これは医者の存亡の危機なのではないかしら。
それはともかくとして、インターネットやAIが日々の診療に関わってきているいま、この効用に期待が大きくなる反面、冒頭に触れたことを始めとして、医者、患者の在り方がもっと変わることが予想される。医学知識が医者だけのものではなく、広く情報を共有していることに、医者は心しなければならないと思うのである。そして、拡がる情報を仕入れるなどして、これまでより柔軟な考えを持たなければならないとも思う。しかし、私は患者さんが知識を持つことに今でも肯定的であることは変わらないのに、どうにも居心地の悪い昨今なのである。すなわち、診察室にいて、科学の進歩の速さが、人間関係にどのように及ぼすのかがわからないのである。いや、AIは医者、患者の在り方が変わったとしても、人と人との間にある機微に、最後まで触れることが出来ないのではないかと思うのである。たとえば、患者さんがAIと話して、心から安心できて、頼もしさや温かさを感じるかどうか。ここにまでAIが至ると、もう医者は不要となる。
世の中が、AIによって一変してしまいそうなことに異議申し立てしたいものの、たった一人では何も出来ない。そういえば、心理学者の河合隼雄が、のどが痛く、咳が出て、鼻水が出た、それを医者に風邪だと診断されることが大事であると、著作中に書いていた。患者さんは、今でいうAIに支配されてはならないということをふた昔以上前に河合隼雄が警告したのではないかと勝手に解釈している。いや、大事なことと思うのだが。
以下は蛇足である。
ある日、肝硬変症に罹った患者さんが下腿に浮腫を生じたため、私は、肝硬変症と下腿浮腫と病名をつけて、利尿剤を処方した。しかし、利尿剤の適応病名である「肝性浮腫」と書かなかったため、診療報酬を請求した際に戻された。何と杓子定規な、と抵抗したところで何の打開も出来ない。これなど、AIに任せてみてみたら、どう判断するだろうかと夢想した。AIのある世の中で、重みがあるものを探すという楽しみはある。
打診、聴診
2019年06月10日
私が臨床経験を積み始めた20代のことである。運よく恩人と言える医師に遭遇した。その医師は、理学所見、つまり患者さんを視て、触って、聴いて得られる情報を殊の外重視した。私にとって、その診察する姿をみることが何よりの臨床教育であった。
そんな彼から、医局と称する医師たちの机を並べた部屋で、ある話を聴いた。すなわち、昔の医師は、肺結核を診断するときに、打診、つまり患者さんの胸に手を当て、その中指を反対の手の指で叩くことにより、肺の中にある空洞を診断したというのだ。空洞は、結核が進展した結果できる形であり、彼は理学所見の重要さを説いてくれたのであった。当時、私は結核療養専門の病院にアルバイト勤務したことがあった。その際に、先輩医師の言葉を踏まえて診察したことがあったものの、私の打診技術では到底診断できなかった。この話は長年忘れていた。
さて、連休も終わって、普通に日常が続くある日に、トーマス・マンの『魔の山』を読み始めた。これは、主人公の青年が、スイスの高原で結核療養することになったことから物語が始まる。結核に罹り診察を受ける際に、「聴診をつづける八分間か十分間、無我夢中で息を吸い込んだり咳をしたりした」「打診で空洞の音までするという」という内容の文章があった。ここを読んでいて、急に40年も前に先輩医師から聞いた件の話を思い出したのである。彼の言葉は、誇張ではなく、打診することによって結核病巣を診断することが当たり前のようになされていたことが、この文章から裏づけられたと思ったのである。それと同時に、昔の医師は、診断に要する設備が限られた中で、今とはちがう努力をしなければならなかったこと、その努力をいま十分に引き継いでいないことなどが頭に浮かんだ。
それはともかくとして、トーマス・マンがこの本を書いた20世紀初頭から比べると、結核に罹患する人は激減した。だから、空洞を診断するにも、対象となる患者さんがいないため、現代の若手医師は、このような機会がないのではないかと思うのである。私が持っている古い診断学の教科書を取り出してみた。三冊の診断学のうち、わずか一冊に「打診時破壺音を呈することがある」と書かれていた。今の診断学教科書には、この文言が記載されているのだろうか。
結核に限らず、時代とともに減る疾病があり、その診断をする機会も少なくなる。そんな中で、昔書かれた書物を読んだり、昔を思い出したりすることは、懐古趣味ではなく、失われつつあるものを再考し、今を戒める機会であると思うのである。何故なら、聴診だけで十分間も要したことを知り、患者さんに新たな気持ちで対峙したいと思ったからである。
日本内科学会
2019年05月08日
日本内科学会に出席した。今年の会場は、名古屋だった。今年は、これまでにない十連休。しかもゴールデンウィークが始まる日に重なるような日程のため、2月の初めにホテルをとろうとしたものの、すでにどこも満室。やっと探したホテルは、最近開業したてのものだった。新しいホテルだったからか、カーナビゲーションで番地、名称、電話番号、どれを入れても検索が出来ない。大体の見当をつけてドライブしたものの、結局見つからず、駅周辺の駐車場に入れて、電話で道順を聞いて、やっとホテルに着くことが出来た。名古屋は大都市ではあるが、内科学会を催すには、小さいのではないかと思った。
毎回、相も変らぬマンモス会場だから、全貌をつかむことなどとても出来ない。いくつもの講演の中で、咳(せき)、痰(たん)に関する話が印象的だった。切り離して考えることが出来ない咳と痰。これらについての診療ガイドラインが発刊され、会場でも売られていた。さっそく購入したこのガイドラインには、咳と痰とが個別に解説されていて、演者によると、痰の診療ガイドラインは、世界初だそうだ。さっそく読み始めているが、治療薬が有用かどうかという基本的なことにも言及しているから、私など臨床医には読み応えがある。各章にFAQ(質疑応答集)がついていて、概略をわかりやすくしてくれている。また、小児についても成人とは別にページを割かれていることもわかりやすい。さっそく、日常の診療に役立てられると嬉しくなった。
学会では、いつも書籍売り場に行くことにしている。都会の書店でさえ比べものにならない量の書籍があり、眺めることの楽しさが満喫できるからである。おかげで、件のガイドラインのほかにもいい本を購入できた。
学会の帰りは、帰省客や観光客のクルマに巻き込まれて、道路は大渋滞。せっかくいい診療ガイドラインを手に入れ、厖大な量の書籍を眺めて、久々に満たされた気持ちが、すっかり遠のいてしまった。今後は、ゴールデンウィークは避けてもらいたいと願っている。
散薬ビン
2019年05月02日
明治村の中に、清水医院という小さな建物がある。中を見学していて調剤棚が眼に入った途端、懐かしさを覚えた。そこには、散薬を入れる7,8センチくらいの筒状の散薬ビンが並んでいて、昔の父の医院のことを思い出したからである。

私の父が当地で開業して数年が経った昭和30年代始め、私は小学校低学年であった。学校から帰ってから、当時は父が薬室と呼んでいた部屋によく入った。そこで、父と母が棚にある散薬ビンから薬を出して計量し、複数の薬を乳鉢の中で混ぜて、三の倍数に並べた薬包紙に分けて、それを包んでいるところをよくみたものである。薬を包む父母のいた薬室は、私の原風景でもある。それだから、明治村では温かいものを感じて、ほっとした気持ちになったのであった。
清水医院は、長野県大桑村に明治30年代に建てられたと説明されている。この明治時代は、私の小学生時代とは、ざっと60年の開きがある。それなのに、同じ光景があったことについて、大雑把に言うと、この60年の進歩は緩やかだったと私には映った。一方で、現代では医学は日進月歩という言葉が代名詞となるくらい、進歩が著しい。その中で、調剤薬はほとんど散薬から錠剤、カプセルになり、毒薬、劇薬はもちろんのこと、処方する数も比べるべくもなく増えた。室内には分包機などが揃い、調剤室は、昭和30年代から新たな60年を経て、その風景も機能も変貌を遂げた。
さて、ある雑誌を読んでいたら、50歳代の医師が医学の進歩についていけないとこぼしていた。60歳代の私は何をかいわんや、であるが、進歩に対する感想はよく聞かれる。最近の進歩事情のすごさを薄々感じていた私は、散薬ビンを見てからというもの、医学は、途中から飛躍的に増えるという指数関数的に進歩していると確信的に思うようになった。そういえば、昔教わった癌細胞の増え方も、ある時点で爆発的となり、こちらも指数関数的増加だったのではないかしら。
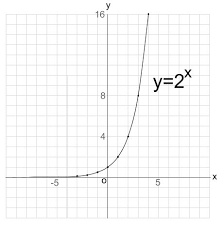
医学の速い進歩に、実は60歳代となった私は、時におののくことがある。一方で、現代の若手医師は、この速さを速いと思っているのかどうかを確かめてみたい気持ちがある。というのも、若い頃と比べると、ずい分と時の過ぎゆく速さを速く感じるようになり、進歩の速さも感覚的なことが加味されているのではないかと疑うからである。つまり、若者には日進月歩の進歩が、そうそう速いものではなくて、ごく普通の出来事と受け止めて、進歩している内容を咀嚼しているのではないかと思ったのである。しかし、進歩に適応するにも限界があるとも思うのである。それに今は、どう生きるか、という生き方も指数関数的に増えていそうであり、その結果、生きがいがなくなるのではないかと危惧するのである。その上、進歩の速い世の中で、温かい心の景色である原風景を抱くことがあるのだろうかと、余計な世話をやいてしまいそうだ。
以上、明治村で眼にした散薬ビンから、医学の進歩や時間感覚に思いが至り、今昔の診療の一部を眺望した。何をどう結論づけたら良いかわからないが、偶然眼にした散薬ビンは、自身の立ち位置を確かめる指標と思えた。
人間ドック
2018年01月10日
10数年前に医院のホームページを作っていたとき、知人が、スタイルシートを用いることにより、保守・点検が楽になる等の助言をしてくれたことがあった。その昔、おでんが好きだったのか、繁華街にあるお店に連れて行ってもらった。そこで意気投合、どんな話題にも長広舌を揮って、まさに博覧強記の人だった。その知人が急逝した。この数年間、病を抱えながら仕事に没頭していたそうだ。倒れてから運ばれた地域の基幹病院で、心臓に関係した死であったと聞いた。そして、病と心臓との関係は、急な経過だったこともあって、わからなかったらしい。
私は遺族から、なぜ急な経過をたどったのだろうかと尋ねられた。病院に通院していたこと以外に手掛かりがさほどない中で、生前に人間ドックを受けていたことを聞いた。かなり若い頃より毎年同じ施設で几帳面に受けていて、亡くなった年まで20年ほどその記録を溜めていた。まさか亡くなる年にも病院通いの傍ら、人間ドックを受けていたとは。後日この検査結果を見せてもらった。それは、その中に因果関係を示唆するような数字の推移がないだろうか、そして、それが見つかれば供養になるのではないか、と思ったからだ。しかし、何年も積み上げられた検査結果に特別な異常値はなく、心電図も正常範囲内であった。
人間ドックの結果の中には、診察結果も記載されていた。私が拝見した一番古いその中に、心雑音あり、の文字があった。ところが、翌年からはその記載はなく、今に至っている。知人からも遺族からも、心臓疾患があったことは聞いていない。
以上、人間ドックでの結果は異常がなく、しかも病状を反映するものは何もなかった。そして、検査医が心雑音を指摘したにも拘らず、精密検査を勧める体制はなかった。それどころか、次年度からは心雑音を指摘していない。結局、多くの検査と診察結果があったものの、遺族の問いに答えられるだけの手掛かりを掴むことができなかった。
人間ドックを受ければ、大多数の人たちは安心するだろうし、だからこそ定期的に受ける人が多いのだろう。知人のように検査値に異常がなければ、検査医はそれ以上の追究はしないだろう。しかし、このたくさんの検査結果を前にして、私は釈然としないでいる。これだけ熱心に毎年通ったことと、病状に検査値は何の回答もしなかったことの落差をどう解釈すればいいのか。遺族に、しんどいと漏らしていた知人。人間ドックで診察した医者には、しんどいと訴えなかったのだろうか。何とかならないかと、人間ドックに、病院とは違う活路を開いてもらおうとしたのではないか。今となっては何もわからない。
検査も大事だが、医者の手、眼、耳でもっと介入できる人間ドックの体制が要るのではないかと切に思う。病を見て人を見ず、と医者は戒められる。知人の死を機に、検査値を見て人を見ず、という言葉も付け加えなければならないと自戒を込めながら思う次第である。
AGと呼ばれる医薬品
2017年09月16日
このところ、オーソライズド・ジェネリック医薬品(AG)が発売されて、我々開業医が処方する薬のうちの一つになっている。AGとは、特許期間中に先発医薬品メーカーの販売許可を受けて、自社などで販売するジェネリック医薬品(ジェネリック)のことである。これは、原薬だけではなく、添加物や製法等に至るまで先発品とまったく同じであるらしい。つまり、先発品が名前を変えただけに過ぎないということだ。これまで出回っていたジェネリックのように、有効成分だけが先発品と同じというわけではないようである。
私は、開業して以来ずっと先発品にこだわって、それを患者さんに処方してきた。ジェネリックを処方しない理由は、患者さんの利益を損なうのではないか等、いくつかある。特に、有効成分だけが同じというジェネリックが、体内で吸収されて効果を表すまで、先発品と同じであるということを、私は理解できないことが主な理由である。処方しない理由とは別に、こんなことがあった。すなわち、病院で処方されたジェネリックを服用している患者さんが当院に紹介された。私が先発品に変えたところ、それまでになかった副作用が出た。この副作用は、説明書に書かれていることであり、珍しい副作用ではなかった。さっそく中止して事なきを得たものの、ジェネリックを服用していた時にはなかったことだった。副作用がないのなら、主作用は果たしてあったのだろうか、あるいは添加物などで副作用を抑えたのだろうか等と邪推したものだ。
処方薬については、医療費の増大を抑えるため、ジェネリックを処方する方向になって久しい。この数年の間に何人もの患者さんが、保険者などから発送された郵便物を持って診察室にやってくるようになった。そこには、先発品をジェネリックに変えることで、1ヶ月にこれこれの医療費が節減される、というようなことが書かれていた。そのような患者さんが多くなり、先発品にこだわることも、もはやこれまで、と思った。それでも、ジェネリックを処方したくない私は、せめてもの抵抗として待合室に、ジェネリックを希望する方は、院外処方せんを発行する旨を掲示することに留めた。
増大する医療費を抑える方策の一環として、ジェネリックを処方、服用するよう推奨していることは理解できる。私も開業医として、医療費を節減するために、いくつかのことはしているつもりである。それなのに、ジェネリックに変えたら医療費を節減できるという郵便物を目にしたとき、まるで、自分は悪いことをしたのではないか、という錯覚に陥ってしまった。それだけではない。高い薬を処方している悪い医者と思われるのではないか、と被害妄想さえ抱いた。薬価差益は無いに等しい今、先発品を購入して収入の一助としている医療機関などどこにもないのに、である。これも、私の心の奥で自分は、本当は善人ではないという意識があるせいかも知れないが、それは、ここでは問わない。
さて、そんな中、AGがどんどん出回るようになった。今では、私は率先してそれを処方するようにしている。先発品と同じものが、他のジェネリックと同じ薬価だからだ。しかし、AGを購入し、ジェネリックに関わるようになってから、何かがおかしいと違和感を抱くこの頃である。先発メーカーが自社の子会社のような組織をつくるなどして、先発品とAGとを作っている。おそらく、生産ラインを新たに作ること、薬品名を登録すること、そしてそれを宣伝することなど、いずれにも費用が発生するだろう。それでも、他のジェネリックメーカーに奪われたシェアを取り戻すことによって得られる利益があるのだろう。しかし、同じものを作るために回り道のようなことをしていて、よく考えたらおかしなことである。また、医療費を抑制するために厚労省は、ジェネリックを処方するよう、そして、服用するよう、ずっと以前からアナウンスしている。何故、先発品を使うなとはっきり言わないのだろう。言わないのなら、先発品とジェネリックとを同一薬価にできないものか。厚労省の力をもってすれば、たやすいことではないか。そして、先発メーカーは、AGなどを作らずに、先発品の薬価をジェネリックと同じにするよう申請したらいかがなものか。
ある新聞に、先ごろ亡くなった永六輔さんを偲んだ一文があった。永さんは、専門家じゃないからこそ言えることがある、と言っていたそうだ。私は医者であるけれど、医療費のしくみや医薬品の製法、流通などについては、知らないことばかりだ。ところが、AGが身近になるにつれ、違和感が増した。目下、私のような違和感を抱く人間が多くなり、おかしいと提言することによって、ひいては、それがより適正な医薬品の流通や医療行為につながらないだろうかと夢想している。

